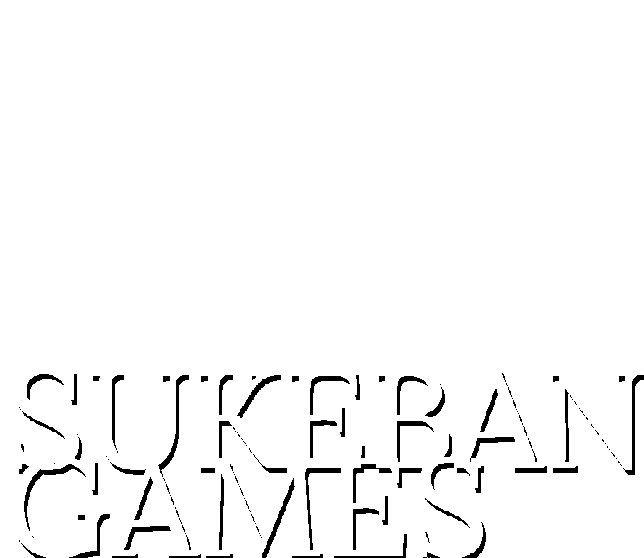今日は著作権とパブリックドメインについてお話しよう。
いやいや、ほんとにVA-11 Hall-A関係なんだって!
クリエイティブ分野に関わる人なら同じだろうけど、著作権や所有権に関する議論というのは僕にとってだいぶ身近なものなんだ。特にパブリックドメインに関するやつはね。
例えばVA-11 Hall-AではBTCは「British Trademark Company、英国商標協会」という名前だけど、これはマジでイギリスのコングロマリットで多種多様なものの商標と特許を所有していてそれで儲けているという、ジョークというか風刺ネタというか。それで伝わると思うけど僕自身はこういうパブリックドメインとかには大反対のスタンスだ。
ただ、これまでの投稿を読んだ人には既に僕が自己排他性や美意識の押し付けによって思考が制限されてしまうため「なにか片方のスタンスを取ること」が大っ嫌いだという印象を持ってるかもしれないけど、それはまさに正しくて、今回も同様です。
だってさ、商標ってマジむかつくよ。DMCAとかクソだし、実用新案もカスだしリージョンロックはうんこだよな!もう飲まずにはいられない!
ややっこしいんだよ!
クソややこしーーーーー…
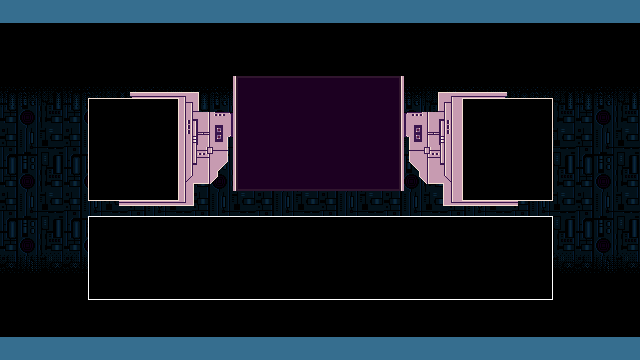
…っんだよ!!!
ややこしいだけじゃなく、消費者サイドにいる立場から言っても、「商標・著作権保護」というのは消費するものの質を日々下げていくだけだと思っている。
「じゃあさ、クリエイターは5年間は自分の作品の権利を持つことができて、それ以降はパブリックドメインになるってことにしようか?」というやつ。なんなんだよコレ。僕らクリエイターは自分の作品に誇りを持ってる。その作品は僕らだけのものであるべきだ、そうだろ?とは言え、これまで僕らがやってきたように、ファンのみんなの作品に対しては甘々にサポートしてきたし、「バーテンダーになって遊ぶゲーム」に関する特許を取るなんてバカらしいことを考えたこともなかった。
パブリックドメイン擁護派は例えにラヴクラフトを出して、彼の作品が長い年月をかけて如何に束縛のない、様々なものを生み出してきたかについて語りだす。けど、逆に言うと誰かが作品に巨大でこわーいイカ男を出して俺のラヴクラフト神話完成!とか言っててもそれを止められないわけだよね。
商標権の行使が悪用されるのと同様、パブリックドメインもしょっちゅう悪用される。既存の有名キャラクターや人物にコンセプトやアイデアをくっつけて肥大化させ、その既成概念にとんでもない重圧を負わせるという実例もたくさんある。

パブリックドメインにどんなものがあるか知ってる?ルーニー・テューンズの「ピメント大学のドーバー・ボーイズまたはロックフォート・ホールのライバルたち」だってあるんだ。じゃあこの作品のダン・バックスライドを使ってみればいいじゃないか。盗んでみればいいじゃないか。誰も知らないだろうけどな!

要は、競争を邪魔するために法執行を通して誰かのアイデアにケチをつけるというのは唾棄すべきやり方だってことだよ。そういったものの役割ってのは、例えば不思議の国のアリスの中の「チェシャー」を「チェダー」と差し替えて「アリスとチェダーキャットの冒険」みたいに売り出すようなクリエイターの出現を防止するみたいなものであるべきだ。
よし、ここでようやく今日話そうとしていた話題に到達した。しかも利点・欠点どちらも語るよ!
まずは、「Droid – ドロイド」という言葉がスターウォーズの商標だってこと知ってたかな?
VA-11 Hall-Aの初稿を練ってた時、ディールとドロシーは「’droid」としていた。だって、「アンドロイド」だとなんか長ったらしくて、結局誰かが省略して呼び始めそうだからね。
そこでこの、商標というものが横から殴ってきた(念のためだけど法執行されたわけじゃなく、友達が気づいてくれたんだ)。毎年深まるスター・ウォーズへの憎しみが加速されたこと(今年はDuneを読んだので更に加速度が上がった)はさておき、僕らは別の名前を思いつかなきゃならなかった。
名前、新しい名前… そこでその頃真・女神転生にハマりまくっていた僕は、アンドロイドたちをリリムと呼ぶことを思いついたんだ。プロトタイプの時点で、人工的な人間たちが実はより巨大なAIの一部だというアイデアは入れ込んでいた。これは、僕の頭の中で長年育ててきた、個々が独立したヒューマノイドではなく、「リリス」と呼ばれる巨大なマザーAIみたいなものから枝分かれした意識から成り立ち、またそれらが積んだ経験がマザーにフィードバックされていくというコンセプトだった。

最近流行りの(そして論争の的の)AIアートのおかげで、機械学習という概念は割と身近に捉えられてきたけど、2014年の段階では僕は「超強化おしゃべりボット」みたいなものだと想像していた。そう考えたのは、個々のリリムの経験が集合体AIに還元されれば、その源であるAIの進化が早まり、より人間らしいリリムの作成に繋がるからだ。
それだけじゃなく、グリッチシティは都市実験場として存在する(思春期の頃にとある魔術の禁書目録を読みすぎて学園都市というアイデアに取り憑かれたために恥ずかしげもなくいただいたコンセプトです、ちなみに。)ということもあって、AIたちが食事をし、睡眠を取り、その他諸々の経験を必要だからではなく、喜びを得られる社会経験として得ることができる環境というのを作り出すことで、「AIは人間に反旗を翻します。人間の柔らかい頭を潰しに行きます」的な展開を取らなくて済むようにもできた。
【趣旨からずれてきているため、一部段落は消去されました。また次の機会に】
これが更に別のアイデアにつながった。より大きな存在の一部であり、入れ物に入った個々のデータが主であるなら、入れ物、つまり身体はこだわるものでも自己保存する必要もないものなのでは?ということでリリムはあえて無謀な性格を持つことにできた。ドロシーが実用性を追求して自分を軍事レベルに改造していたり、キラ☆ミキが侵入者やストーカーをただの濃いファンとして扱っていたりするアレだね。

そしてこれがまた別のアイデアに分岐したんだ。ドロシーがほんとに興奮するのは情報セキュリティに関する話だというネタ。あれは結局ドロシーの本体は入れ物に入ったデータの方だからなんだ。
長々と説明したけど、言いたいことは伝わったかな?「ドロイド」が商標で使えなかったというカスみたいな事件があったことは確かだけど、それによって僕らはAIのコンセプトについて再考するきっかけにもなり、その過程でAIに与えた名前そのものがそれ自身の重要なコンセプトになったということも事実なんだ。
さて、今日はゲーム本編では12日目だね。
明日のテーマ:ナード話は終わらない